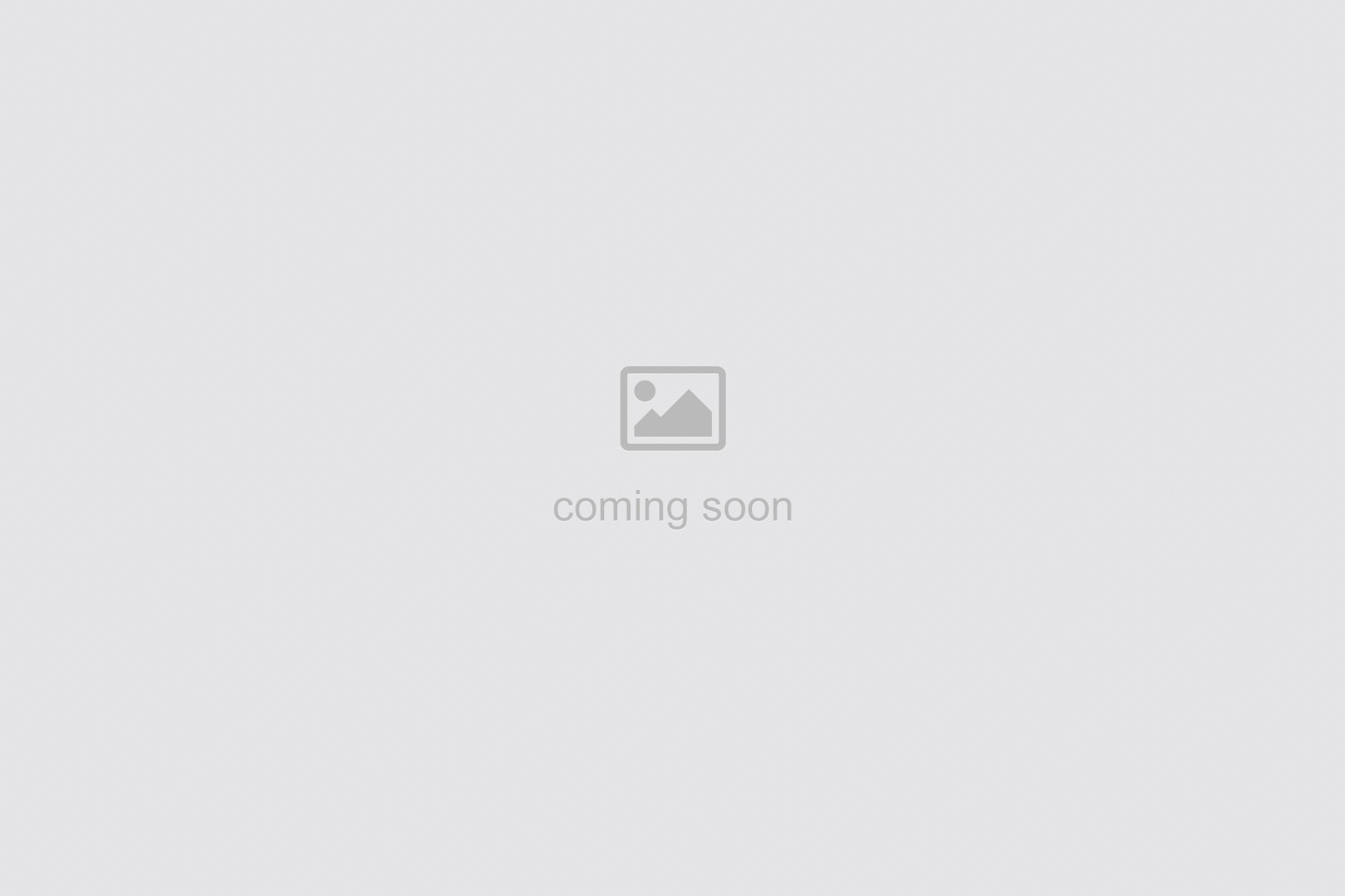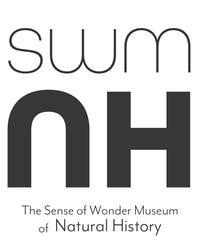
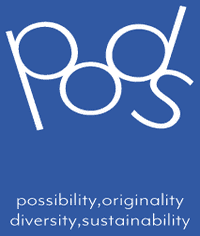
あなただけの 答えを探して。
他県からの転入や核家族化など
園児を取り巻く環境も様々。
しかし、私たちの周辺にはたくさんの
美しい自然の原風景があります。
大切な人と、そんな自然のなかに
冒険出来たなら
そこが子どもたちのふるさとになるはず。
そして、きっと共に過ごした
温かな思い出は
一生心の底辺に静かに佇むでしょう。
私たちの足元は
こんなにも輝いています。
*フィールドワーク実績*
・淡水魚採集(武雄川)
・干潟の生き物探し(イマリンビーチ)
・天山登山
・ウミホタル観察(唐津)
・有明海干潟体験
・宇宙科学館裏山探索
・ビオトープの水抜いちゃいました大作戦(園庭)
・長崎市立恐竜博物館ツアー
・鏡山登山(唐津)
・宇宙科学館ツアー
・せせらぎプロムナードの生き物探し
・中古庭ダム周辺川生き物探し
すべては自分のルーツを知るため。
ここで自分だけの答えを見つけたら
もう大丈夫。

Science Day
「虹の上を歩きたい」
「空を飛んでみたい」
子どもたちのそんなつぶやきが実現できたなら。
自然科学講師と一緒に
子どもの「なぜ?」「ふしぎ!」
の世界へ飛び込んでみましょう。
ミニコラム 「羅針盤のこころ」
おねがいごと
2022-09-13
あたらしい なかま
2022-08-29
想像のチカラ
2022-08-12
サイエンスデイでクエン酸や酢、重曹を使って色水の実験をした4,5歳児さん。それからお家で実験したり、ブルーベリー等を持ってきて実験したり。子どもたちの興味が広がって、それを自分たちで実現しています。
行事で終わらせないのは、想像のチカラと、実現するチカラ。
それが夢見るチカラとなるのでしょうね。
親子で実験してみませんか
2022-08-19
年長のクラスでは、自分色探しの真っ最中、そして「虹色」の作り方を模索中。春はピンクのツツジ、黄色のキンシバイ、イチゴ。でもなかなか染まりません。
キッチンの先生から「玉ねぎはどう?」と聞いて、収穫後の玉ねぎを鍋でコトコト。見事茶色に染まりました。
子どもたちは思い思いに輪ゴムで布を縛り、ミョウバンを入れた玉ねぎの煮汁に漬け込みました。
翌日、白い布が茶色から鮮やかな黄金色に。その時の子どもたちの表情といったら。そこから膨らむ話し合い。
「トマトは?ぶどうは?なすびもできそう」と小さな博士たちの研究が始まりました。
お家でもお子様と一緒に自分色を探して染めてみませんか?失敗しても大丈夫。
「染まらなかったね、お母さんも紫になると思ってたよ。」と大人だって知らないことがあると分かれば、きっと子どもたちも安心するでしょう。
♡宜しければご家庭でお子様と実験され、染まったものと染まらなかったものを教えていただけたら嬉しいです。
〔 染物の材料 〕
1.子どもたちが染めてみたいと思った植物や野菜など
2.鍋(煮込み用)または袋(モミモミ用)
3.ボール
4.白布・輪ゴム
5.焼ミョウバン(色落ち防止の効果あり。お湯で溶かしてから使ってください。)
〔 染め方 〕
煮込んでできた煮汁か、揉んで出た汁と焼きミョウバンをボールに入れて混ぜます。そこに輪ゴムで縛った白布を入れ、数時間から1日放置で完成。
〔 色の変化を楽しむためのプラス実験 〕
1.酢
2.レモン水
3.炭酸水
4.重曹
5.クエン酸
〔 染め方 〕
5つの容器に1~5を分けて用意し、染物の煮汁も5つの容器に分けて用意します。ミョウバンも入れてくださいね。それぞれに白布を入れ、色の変化を楽しまれて下さい。
本物がもたらす力
2022-08-26
強炭酸水にメントール系ラムネを入れるとどうなるだろう?と始まった4歳児さんの園庭での実験。2クラス、仲良く半分こして始まりました。みんなドキドキバクバクしながら、いつでも逃げられる準備OK!!
「いくよ~!!」
ドキドキドキドキ・・・・・・・
シ~~~ン・・・・
・・・・・まさかの不発でした。しかし、そこで出た子どもの言葉は、「なんでできなかったんだろう?」だったのです。
どんなに素晴らしい実験の成功よりも、この「なんで?」という気持ち。これが本物にふれる一番の成果です。
実験、大成功♪